
自動車保険の『等級』って結局どういう仕組み?

「自動車保険の更新で“等級が1つ上がりました”と聞いたけど、正直どういう意味?」
「事故をして保険を使ったら“等級が下がります”と言われたけど、いくらぐらい変わるの?」
こんな疑問を持ったことはありませんか?
自動車保険に加入している方なら、必ず関わるのが『ノンフリート等級制度』。これは、契約者一人ひとりの事故実績に応じて保険料を割り引いたり割り増ししたりする仕組みです。実はこの等級制度をきちんと理解しているかどうかで、長い目で見たときに保険料に大きな差が出てきます。
この記事では、等級の基本的な仕組みから、事故時の影響、賢い付き合い方まで分かりやすく解説していきます。
等級制度とは?
自動車保険には「ノンフリート等級制度」という仕組みがあります。これは、主に自家用車を契約する個人や小規模事業者を対象とした制度で、1等級から20等級まで存在します。
等級は契約者の“運転の安全度”を表すようなイメージで、数字が大きいほど「事故を起こさず安全運転を続けている」と評価されます。逆に、事故を起こして保険を使うと等級が下がり、割増の対象になる仕組みです。
- 1等級 … もっとも割増が大きく、保険料は高い
- 20等級 … もっとも割引率が大きく、保険料は安い
例えば、6S等級(自動車保険の新規契約で最初に入る等級)は3%の割増からスタートします。その後、無事故を続けると等級が上がり、20等級になると最大で63%の割引を受けられるのです。
等級の進み方と下がり方
基本的なルールはシンプルです。
- 1年間「無事故」で過ごす → 等級が1つ上がる
- 保険を使って事故対応する → 等級が3つ下がる
たとえば、10等級で契約している方が1年間事故なく更新すれば翌年は11等級になります。しかし、もし事故を起こして保険を使うと翌年は7等級に下がってしまいます。
さらに、事故で保険を使うと「事故有係数」という仕組みが働き、1〜6年間は割引率が通常よりも低く設定されます。これにより、保険を使った翌年以降は数年間にわたって保険料が高くなり続けることになります。
事故で保険を使ったときの影響
「少しの事故でも保険を使った方が得だろう」と考える方は多いですが、実際にはそうとも限りません。
例えば、修理費用が15万円で保険を使った場合、翌年以降の3等級ダウン+事故有係数による割引減少で、数年間で20万円以上保険料が増えることもあります。そうなると「使わずに自己負担した方が安かった」という結果になってしまうのです。
逆に、高額な修理や人身事故の場合は迷わず保険を使うべきです。どちらにしても「保険を使うべきかどうか」を冷静に判断することが、長期的に見て家計の負担を軽減します。
よくある誤解
等級については、実際のご相談の中でもよく誤解されている点があります。
- 「家族で等級を共有できるの?」 → 等級は契約ごとに管理され、家族でまとめることはできません。ただし契約者や車の入れ替え時に“等級を引き継ぐ”ことは可能です。
- 「車を買い替えたら等級はリセットされる?」 → 車を変更しても契約を継続すれば等級はそのまま引き継げます。
- 「一度下がったら元に戻らない?」 → 無事故を続ければ毎年1等級ずつ上がっていき、元の等級に戻すことができます。
賢い等級の守り方
- 小さな事故はシミュレーションを
修理代と将来の保険料アップを比較して、どちらが有利かを確認しましょう。 - “使っても等級に影響しない特約”を活用
弁護士費用特約やロードサービスなどは、利用しても等級に影響しません。安心して使える補償は積極的に活用しましょう。 - 代理店に必ず相談
「使うべきかどうか分からない」ときは、自己判断せず代理店に連絡を。将来の保険料まで見据えてアドバイスしてもらえるので安心です。
まとめ
自動車保険の等級は、単なる数字ではなく「保険料に直結する評価制度」です。
- 無事故を続ければ割引率が増えてお得に
- 事故を起こして使うと3等級ダウン+数年間の保険料アップ
- 判断に迷うときはまず代理店へ相談
等級制度を理解しておけば、いざというときに「保険を使う?使わない?」の判断も冷静にできます。長期的に家計を守るためにも、ぜひこの機会にご自身の等級を確認してみてください。
✅ エクセルライフでは、事故時の対応はもちろん、「保険を使うかどうか」のご相談にも丁寧にお答えしています。お気軽にご相談ください!
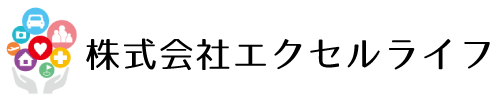









コメント