
福利厚生としての“保険の活用術”

〜社員を守り、会社を強くする仕組みづくり〜
~はじめに~ 社員の安心が、会社の成長を支える
近年、社員の定着率や採用力を高めるために「福利厚生の充実」を重視する企業が増えています。
特に中小企業では「大企業のような福利厚生制度は難しい」と感じる経営者も多いですが、
実は“保険”をうまく活用することで、コストを抑えながら社員満足度を高める仕組みをつくることができます。
本記事では、**経営にプラスになる「保険を使った福利厚生の仕組み」**について分かりやすく解説します。
福利厚生としての保険の位置づけ
福利厚生とは、給与以外で社員の生活を支援する制度全般のことです。
健康保険や年金などの法定福利厚生に加え、企業が独自に導入できる“任意の福利厚生”もあります。
その中で「保険」は、次のような場面で大きな力を発揮します。
- 病気やケガによる休業時の収入補償
- 万が一の死亡保障
- がん・生活習慣病などへの医療サポート
- 退職金や企業年金制度の代替としての積立型保険
- 経営者リスクや役員保障のカバー
2. 福利厚生で使われる主な保険の種類
① 団体定期保険
社員が在職中に亡くなった場合、遺族に保険金が支払われる仕組みです。
掛金が比較的安く、福利厚生制度として導入しやすいのが特徴。
「会社が社員を守る」というメッセージを伝えやすく、離職防止にもつながります。
② 団体医療保険・がん保険
病気やケガで入院・手術をした場合に備える保険です。
個人で加入するよりも保険料が割安になり、加入手続きも簡単。
がん保険や三大疾病保険を団体契約で用意する企業も増えています。
③ 企業型の所得補償保険
社員がケガや病気で働けなくなったとき、一定期間収入を補償する保険です。
特に営業職や技術職など“人が資産”の業種では、社員にとって大きな安心材料になります。
④ 養老保険・積立保険(退職金・慶弔金対策)
社員の退職時や一定年数の勤続時に保険金を受け取るタイプ。
企業の「退職金制度」「慶弔金制度」の代替や補完として活用されています。
保険料の一部を資産形成として積み立てられるため、会社の財務戦略にも役立ちます。
⑤ 役員・経営者向け保障
役員や経営者が病気・事故に遭った場合のリスクを補う保険。
「会社を守るための経営保障」として導入されるケースが多く、
事業継続や後継者問題のリスクヘッジにもつながります。
福利厚生保険を導入する3つのメリット
① 採用・定着率の向上
「社員を大切にしている会社」という印象を与え、採用競争力を高めます。
また、既存社員のモチベーション維持にも効果的です。
② 経営の安定化
病気や事故による突然の離職・休職は、企業にとっても大きな損失です。
保険を活用してリスクを分散することで、経営の安定にもつながります。
③ コストメリット
福利厚生として支払う保険料は、全額損金算入できるケースもあります。
節税効果を得ながら社員の安心を守れる、非常に効率の良い制度設計が可能です。
導入のポイント:まずは現状把握から
福利厚生保険を導入する際は、次の3ステップを意識しましょう。
- 社員構成の把握(年齢層・家族構成・勤務年数など)
- 既存制度の確認(すでに加入している保険や社会保険)
- 目的の明確化(採用力アップ/リスク対策/退職金準備など)
これらを整理した上で、会社に合った制度を設計することが重要です。
特に、加入する保険の種類や掛金の扱い方によっては、税務処理上の注意点もあるため、
保険の専門家と相談しながら進めるのがおすすめです。
エクセルライフがサポートできること
私たちエクセルライフでは、
企業の規模や業種、経営方針に合わせた最適な保険設計を行っています。
「福利厚生として保険を導入したいけど、どこから始めればいいか分からない」
「既存の保険を見直して、社員満足度を上げたい」
そんなご相談を多数いただいています。
単なる“保険の提案”ではなく、
経営戦略の一部としての“福利厚生プランニング”を行うことで、
社員にも会社にもメリットがある制度設計をご提案いたします。
まとめ
福利厚生における「保険の活用」は、
社員を守るだけでなく、会社の信頼やブランド価値を高める重要な要素です。
「社員を大切にする会社」ほど、業績も伸び、良い人材が集まります。
保険を“経費”としてではなく、“投資”として考える視点を持つことが、
これからの企業経営には欠かせません。
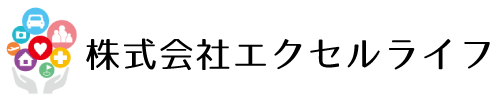









コメント